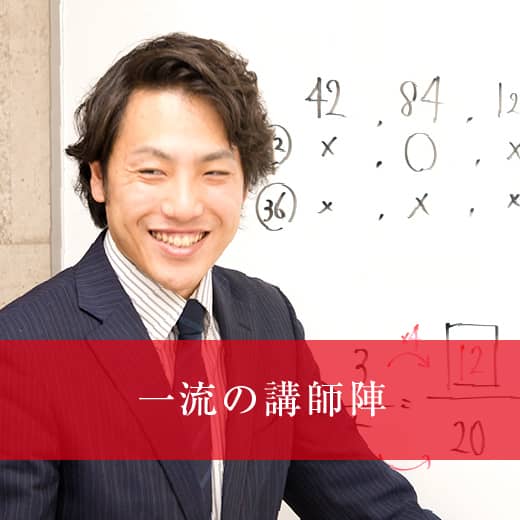2025/09/15
高富校
山田 陽介
中学生向け
多様性と子供の自由は全く違います

最近、教育の場でよく耳にする「多様性」。
一人ひとりの個性を尊重し、大切にする考え方はとても素晴らしいものです。
ただ時に、この「多様性」と「子供を自由にさせること」を混同してしまうことがあります。
塾での出来事です。
ある生徒が宿題をしてこなかったときに、こう言いました。
「僕は自分のペースで勉強する方が合っているから、宿題はやらなくてもいいと思う」
確かに、勉強の仕方やペースには個性があります。
しかし宿題は、ただ子供を縛るためにあるのではなく、授業で学んだことを定着させるための最低限のトレーニングです。
それを「自由」という言葉で避けてしまうと、本人が力をつけるチャンスを失ってしまいます。
私はその子にこう伝えました。
「君のやり方を尊重することは大事だよ。でも、みんなで学ぶ上で守らなきゃいけないルールや、最低限の練習は外せないんだ。
その上で、自分なりの工夫を加えるのが“多様性”なんだよ」
ここで大切なのは、「自由=やりたいことだけやっていい」ではないということ。
自由には責任やルールが伴います。
多様性とはルールをなくすことではなく、その枠の中で自分らしさを発揮していくことです。

実は家庭生活の中でも、同じような場面は多くあります。
ゲームの時間
「僕は夜の方が集中できるから、宿題は後でやるよ」
→ けれど結局眠くなってできない…。
これは多様性ではなく、ただの「やりたくない」の言い訳です。
ルールとして「宿題を終えてからゲーム」という順序は守らせ、その上で「どの宿題から始めるか」を子供に決めさせると、自由と責任のバランスが取れます。
部屋の片づけ
「私は散らかっている方が落ち着くの!」
→ 本当に落ち着いているのなら個性かもしれません。
でも家族が迷惑を感じるレベルなら、それは“自由”ではなく“わがまま”です。
「自分のコーナーは好きにしていいけど、共有スペースは片づける」という線引きが大切です。
こうした小さな日常の積み重ねこそ、子供に「自由」と「責任」の違いを教える大切な場面になります。

ご家庭でできる工夫として、以下のようなことがあります。
★「やりたくない理由」を一緒に考える
「嫌だから」ではなく「なぜ嫌なのか?」を聞き出してみましょう。
→ 「分からないから」「時間が足りないから」など理由が分かれば解決策を一緒に考えられます。
★ルールと選択肢をセットにする
「必ずやること」は決める。
ただし「やる順番」や「取り組む時間帯」は子供に選ばせる。
こうすると「やらされ感」が減り、前向きに取り組めます。
★できたことをしっかり認める
「やるべきことをやった」ことを評価する。
その上で「どう工夫したか」を一緒に振り返ると、子供の自信と個性につながります。
ご家庭でも、子供が「自由」を主張したときに、
それが「責任からの逃げ」なのか、「自分らしい工夫の芽」なのかを見極めることが大切です。
多様性を大切にしながらも、自由と責任のバランスを教えていくこと。
それが、子供たちが将来、社会の中で自分らしく輝くための大切な準備になると、私は日々の指導を通して強く感じています。