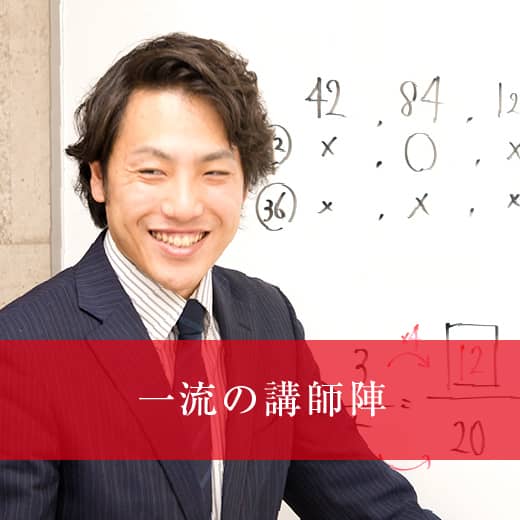2025/08/19
高富校
吉田 一平
小学生向け
家庭学習で親がやってはいけない7つのNG行動

今回は小学生の親さん向けに、子どもとの家庭での接し方のコツについて紹介していきます!
ぜひ参考にしてみてください!(^^)!
1. 散らかった環境を放置する
学習前の散らかった机や部屋は、子どもの集中力を著しく削いでしまいます。
学習に入る前に、机の上だけでもスッキリ整理し、目に入るゲームやおもちゃなどは片付けておきましょう。
親子で一緒に片付ける習慣を取り入れると、学習への切り替えもスムーズになります!
2. 宿題を「やらなければいけないもの」にしてしまう
「宿題を終わらせないと○○できないよ」「これをしないと大変なことになるよ」といった声かけは、宿題自体を重荷として子どもに感じさせてしまいます。
こうした言い回しは、学習を苦痛な義務と認識させ、やる気を削いでしまいます!
自ら宿題をできるように、子どもとルールを決めるのがコツです。
3. 細かすぎる指摘で子どもを萎縮させる
「字が少し曲がっている」「ここは5番じゃない」など、細かいことを逐一指摘すると、子どもは「自分のやり方」と「親の期待」のギャップに戸惑い、学習を楽しめなくなることがあります。
時には気になる部分をそっと見守ることも大切です!
4. 間違いだけを責めるスタイル
子どもの答案で間違いだけを指摘するのは避けましょう。
「ここが間違っている」「また失敗したね」と言われ続けると、子どもは「間違えた自分=ダメな自分」と感じてしまいがちです。
まずは「ここはよくできたね」「惜しいところまでいってるね」と前向きに声をかけ、間違いは「改善のチャンス」と捉えましょう。
5. 説明を長く続けすぎる
「つい教えてあげたくなる気持ち」はよくわかりますが、長すぎる説明は子どもの集中力を切らせてしまうことがあります。
必要な内容に絞って、“やり方”や“考え方”のポイントだけ、短く伝えるよう意識しましょう。
6. 子どもの意見や意思を無視しすぎる
子どもの意見を尊重せず、「親の考えだけで進路や学習計画を決める」のは避けたいところです。
自分の考えが尊重されることで、子どもは“自分で決める力”や“やる意味”を実感しやすくなります。
アドバイスは必要ですが、最終的な決定や方向性は子ども自身に委ねるスタンスでいましょう。
7. 過干渉になりすぎる
「勉強しなさい」「今すぐやりなさい」と、細かく口出ししすぎると子どもはストレスを感じ、反抗心や無力感につながりかねません。
子どもには自分のペースで学ぶ権利があります。必要なときだけサポートし、「信頼して見守る」姿勢を大切に。
子どもの「やる気」を引き出したり、学習習慣を定着させるには、親の関わり方がとても重要です。
ただ叱ったり管理したりするだけでは、本当の意味で子どもの学びの力にはつながりません。
-
安心できる環境づくり(整理整頓された学習スペース・親の背中を見せるなど)
-
認める声かけ(努力やちょっとした成長に気づいて伝える)
-
選ばせること(「今日はどれをどれくらいやりたい?」と、子ども自身に計画させる)
-
短く、ポイントで伝えること(必要最小限の説明に絞る)
このような配慮が、子どもの「自ら学ぶ力」や「主体性」につながっていきます。
学習の質を高める親のデザイン力を、一緒に育んでいきましょう!