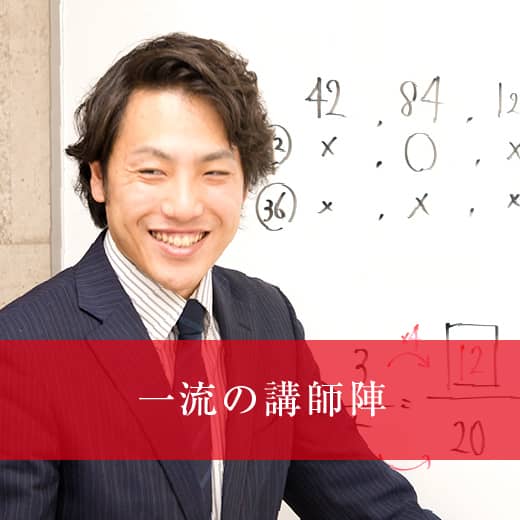2025/02/19
2025年の共通テスト数学
2025年の大学入学共通テストの数学は、
新学習指導要領の導入に伴い、
大きな変化がありました。
特に、数学ⅠAと数学ⅡBCの試験内容や構成が刷新され、
受験生に新たな対応が求められました。
数学ⅠAの主な変更点
- 大問構成の変更:従来の大問5問から大問4問に再編成されました。選択問題であった「整数」が削除され、「図形の性質」と「場合の数・確率」が必答問題となりました。これにより、全ての受験生がこれらの分野を解答する必要があります。
数学ⅡBCの主な変更点
-
科目名の変更:「数学ⅡB」から「数学ⅡBC」に名称が変更され、出題範囲が拡大しました。新たに「数学C」の内容である「ベクトル」や「複素数平面」が加わり、より高度な理解が求められます。
-
試験時間と問題数の増加:試験時間が60分から70分に延長され、大問数も7題に増加しました。受験生は必答の3題に加え、選択問題4題の中から3題を選んで解答する形式となり、時間配分と戦略的な選択が重要となります。
-
新たな出題範囲:「統計的な推測」や「複素数平面」など、新課程で追加された内容が出題されました。特に「統計的な推測」では、仮説検定や信頼区間に関する問題が登場し、データ分析の理解が求められました。
これらの変更により、
受験生は従来の学習内容に加え、
新たな範囲の学習と柔軟な思考力が
求められるようになりました。
日頃から幅広い分野の基礎を固め、
問題演習を通じて応用力を養うことが、
高得点への鍵となるでしょう。